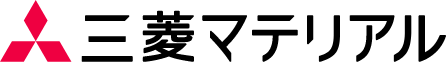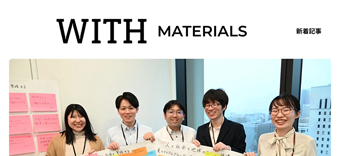- ホーム
- サステナビリティレポート
- 三菱マテリアルのマテリアリティ(重要課題)
- サプライチェーンにおける人権への配慮
Enhancement of Sustainable Supply Chain Management 持続可能なサプライチェーンマネジメントの強化
サプライチェーンにおける人権への配慮
責任ある原材料調達
| 活動テーマ | 2023年度の活動実績 | 自己 評価 |
2024年度以降の活動目標・予定 |
|---|---|---|---|
|
|
B |
|
|
|
A |
|
自己評価 A:目標達成 B:概ね目標達成 C:目標未達成
基本的な考え方
当社は総合素材メーカーとしてバリューチェーン全体で多くの取引先との協働し、共生を促進することで付加価値を向上させています。また、「製品の安定供給」や「製品の競争力強化」を目指し、グローバルな調達活動を積極的に展開しています。
安定した調達は操業の安定化と機会損失の減少につながるため、公平・公正な取引、腐敗防止、法令遵守、人権等に配慮し、取引先と社会や環境への負の影響を予防・軽減する協力関係の構築を目指しています。
三菱マテリアルグループ調達方針
- 門戸開放・公正な取引
- 私たちは、サプライヤー選定にあたり、全てのサプライヤーの皆様に広く取引の機会を提供いたします。
また、サプライヤーの選定は、相互信頼に基づく取引より共存共栄を実現することを目指し、品質・価格・納期・経営基盤等を公平かつ適正に評価して行うものとします。 - 法令遵守
- 私たちは、調達を行うにあたり、国内外の法令を遵守いたします。
- 調達倫理の遵守
- 私たちは、調達を行うにあたり、サプライヤー等との不適切な利益の授受は行いません。
- 労働環境・労働衛生
- 私たちは、調達を行うにあたり、労働環境の向上や労働衛生の確保を推進いたします。
- 環境保全・脱炭素化
- 私たちは、調達を行うにあたり、環境保全に努め、脱炭素化、資源の有効活用とその再資源化に取り組みます。
- 人権尊重
- 私たちは、調達を行うにあたり、国際的に宣言されている人権の原則を尊重します。
- 情報セキュリティ
- 私たちは、調達を行うにあたり、サプライヤーの皆様他から得た情報等の機密を厳格に管理いたします。
私たちは、調達を行うにあたり、本取組みを原材料調達から素材・製品の開発、生産、流通、消費、廃棄そして再資源化を含むすべての事業活動の中で推進いたします。
(制定日 2021年12月1日)
物流資材部門・CSR調達ガイドラインの運用
当社では、グローバルなサプライチェーンにおけるCSR課題に対する組織的な対応力強化のため、「物流資材部門CSR調達ガイドライン」を取引先へ周知し、内容を相互に確認のうえ契約書を締結する等の取り組みを行っています。本ガイドラインは、銅精鉱以外の原材料・資機材を対象とし、公正な取引、人権尊重、法令遵守、調達倫理、労働衛生、環境保全、情報セキュリティ等、当社が守るべき項目として当社の上位方針である「調達基本方針」と、これら項目に加え、公正な事業活動、労働環境整備・労働時間、結社の自由、責任ある原料調達、製品の品質と安全性等に関して取引先に遵守をお願いする「CSR調達基準」から構成されています。
当社では、取引先での取り組みの実効性を確保するため、2016年4月より実施しているサプライヤー採用審査およびサプライヤー評価を行い、必要に応じて現地監査も実施しています(2023年度においては現地監査を2社実施)。
新規に取引を開始する取引先に対しては、取引開始前に「サプライヤーセルフチェックシート」による自己評価を実施しています。このセルフチェックシートでは、従来の品質、価格、納期等の一般的な項目に加えて、2023年度からは、取引先におけるCSR、人権、労働・安全衛生、談合やカルテル・優越的地位の乱用等の腐敗防止に関する項目を含めた企業倫理、環境保全に対する方針、体制、取り組み、是正の仕組みに関する設問を追加し、児童労働・強制労働、不当な低賃金労働等の人権面や、環境への悪影響等といった調達に関わる社会的責任への取り組みについても確認を行っています。物流資材部門において、セルフチェックシートの回答内容を基に採点を行い、総合評点に応じた対応方針を決定します。
既存の取引先に対しては、主要品目の調達先を中心に重要な取引先として選定し、「サプライヤーセルフチェックシート」を用いた自己評価を実施後、情報セキュリティや品質管理、納期管理、談合やカルテル・優越的地位の乱用などの腐敗防止等の計28の審査項目からなる総合的なパフォーマンス評価を実施します。パフォーマンス評価結果に応じて必要な是正指導を行っています。
なお、2023年度の「サプライヤーセルフチェックシート」の回収数は、新規取引先25社、既存取引先194社の計219社でした。全ての新規取引先に対して採用審査を実施し、既存取引先194社の内の168社に対して定期評価を実施しました。審査および評価を実施した結果、評価基準点を下回り、高リスクとなった取引先はありませんでした。
また、2024年度からは「サプライヤーセルフチェックシート」によりサプライチェーン上に人権リスクがあると判断した取引先に対して、人権デューデリジェンスを実施し、取引先の改善を促進していくことでサプライチェーン全体の改善を図っていくようにしています。
サプライヤーセルフチェックシートによる確認項目(一例)
- 気候変動や地球温暖化防止への対応として、温室効果ガスの削減目標の設定や取り組み、是正する仕組みの有無
- 水資源をはじめとした資源の有効利用、大気や水質の汚染をはじめとした環境に関する国内外の法規制や社会規範/業界規範および規格の認識、方針やガイドライン、管理体制の有無
- 団体交渉権に関する取り組み、是正する仕組みの有無
- 労働時間の管理や有給休暇取得の権利保護に関する取り組み、是正する仕組みの有無
- 操業国や地域の法定最低賃金を遵守する取り組み(労働協約の締結、割増賃金、支払方法等の適切な運用)、是正する仕組みの有無
銅製品の原料調達における取り組み
銅製品の原料である銅精鉱については、出資先である海外鉱山からの買鉱を中心とした調達を行っており、国内の製錬所へ安定的に供給しています。当社は、直接的な鉱山経営を行わないノンオペレーターの立場ですが、グローバルな調達活動をする企業として持続可能な開発への責任を果たしていきたいと考えています。
当社は、国内外のグループ会社において、一定規模の権益を有する鉱山のアドバイザリー・コミッティーに特定の人員を参加させるなど、先住民の方々や地域コミュニティーとの対話を重視しています。
また、買鉱先の鉱山会社に対しては、当社が出資する前にサステナビリティ投融資ガイドラインやCSR調達基準への遵守を要請するとともに、遵守状況の確認のために定期的にアンケート調査等を実施し、必要に応じて状況の把握や改善を申し入れています。さらに、環境保全や人権尊重をグローバルなサプライチェーンの管理における重要な考慮事項と位置付け、これらを事業プロセスに組み込んでいます。
「金属事業カンパニー CSR調達基準」の概要
【環境パフォーマンスの継続的な改善】
- 継続的な改善を重視した環境マネジメントシステムの導入・運営
- 鉱山の開発・運営における環境負荷の低減
- 自然保護区域への配慮、生物多様性の保護
- 環境問題に関するステークホルダーとの協議
【労働安全衛生の継続的な改善】
- 継続的な改善を重視した労働安全衛生マネジメントシステムの導入
- 従業員および業務委託業者の労働災害の防止、地域住民を含めた疾病の発生予防策
【基本的人権の保護】
- 強制労働、児童労働の防止
- ハラスメント、不当な差別の排除
- 強制的な住民移転の回避・補償
- 先住民の保護
- ステークホルダーからの苦情、紛争の管理・記録
- 紛争地における人権侵害が懸念される武装集団などへの直接的、間接的関与の排除
「金属事業カンパニー サステナビリティ投融資ガイドライン」の概要
【倫理的なビジネス】
・法令遵守
・腐敗防止
・政府機関への納付金とEITI(資源採取産業透明性イニシアチブ)の支持
・サステナビリティガバナンス
・サステナビリティに関する外部認証の取得
【リスク管理】
・環境・社会リスクの評価
・環境・社会リスクのマネジメント
・緊急事態対応計画の策定
・紛争・高リスク地域への適切な対応
・取引先・業務委託者等の責任ある行動の促進
【人権】
・強制移住・経済損失の回避
・安全・人権に関する自主原則の尊重
・児童労働の禁止
・強制労働の禁止
・結社の自由・団体交渉権の尊重
・最低賃金の遵守、法定外労働時間の遵守
・先住民の生活・権利等の尊重
・FPIC(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)の実施
・女性の権利尊重、差別・ハラスメントの禁止
・苦情処理メカニズム
・ステークホルダーエンゲージメント
【安全衛生】
・安全衛生の施策の実施・モニタリング
・安全衛生に関する教育と健康状態のモニタリング
【環境パフォーマンス】
・閉山計画の策定
・適切な水の管理・持続的な水の利用等
・適切なテーリングの管理
・汚染の防止、適切な廃棄物の処理
・エネルギー効率の向上、GHG排出量の開示
・保護地区の尊重
・生物多様性へのインパクト・リスク評価
【地域コミュニティ】
・コミュニティの発展のサポート
・コミュニティの企業への経済機会の提供
・小規模鉱業(ASM)のサポート
サフラナル銅鉱山プロジェクトにおける環境影響評価
当社はテックリソーシーズ社(本社 カナダ)およびその子会社とともに、ペルーにおいてサフラナル銅鉱山プロジェクトに参画しています。
このプロジェクトでは、カンパニア ミネラサフラナル社(CMZ社)がオペレーションを担当しており、当社の実質的な出資比率は20%です。当社は、ペルー国内に子会社を設立のうえ、CMZ社と連携して現地の状況を常に把握しつつ、本プロジェクトの推進に取り組んでいます。
CMZ社は、地元の文化、価値観、伝統、歴史的遺産を尊重し、オープンで誠実な長期的パートナーシップを結ぶことを行動規範に掲げています。そのため、本プロジェクト実施区域周辺の地域住民やステークホルダーとの公式な対話の場を設け、個別にブリーフィングの実施や問い合わせへの対応等も行っています。このような活動を通じて、地元の意見や要望を反映しながら、社会的な信頼の構築に努めています。
また、環境影響評価の許認可取得前には地域住民との対話を重ねてきたほか、将来の鉱山およびインフラ整備地域における環境・地域社会に関する基礎調査も実施してきました。
責任ある鉱物調達・製錬事業者として
「紛争鉱物管理」から「責任ある鉱物調達管理」へ
米国の「金融規制改革法」は、コンゴ民主共和国(DRC)およびその隣接国の鉱物が、人権侵害や暴力行為を行う反政府軍の武装資金源となることを防ぐため、米国上場企業に対し、タンタル、錫、タングステン、金の4鉱物(3TG)を「紛争鉱物」と定義し、原産国の調査と調査結果の開示を義務付けています。近年、EUを中心に「紛争鉱物」の範囲が拡大し、より広く「責任ある鉱物調達」という観点からコバルトや銀についても検証の対象となっています。この動向に連動して、OECD(経済協力開発機構)やSEC(米国証券取引委員会)のほか、RMI※1やLBMA(ロンドン貴金属地金市場協会※2)やLME(ロンドン金属取引所※3)等が、紛争鉱物問題(責任ある鉱物調達管理)に関するガイダンス等を策定しています。
当社は、金、銀、銅、鉛および錫を製錬する責任ある事業者としてこれらの世界的な要請に対応するため、金属原料の生産者や取引業者に対して効率的なデューディリジェンス基準に基づいた調査を行う等の取り組みを進めており、関連方針を策定し公開しています。
- ※1 RMI:Responsible Minerals Initiative 責任ある鉱物イニシアティブ
- ※2 LBMA:The London Bullion Market Association 貴金属市場で流通する貴金属地金の品質等を管理する協会
- ※3 LME:London Metal Exchange 世界最大規模の非鉄金属中心の取引所
当社の「責任ある鉱物調達方針」に反する行為があった場合、「責任ある鉱物調達ホットライン」にご連絡ください。
金属事業カンパニー(金、銀、錫に関する取り組み)
当社金属事業カンパニーでは、2011年6月からEITI※1(採取産業透明性イニシアチブ)が推進する「鉱物資源に関わる資金の流れの透明性確保に向けた活動」に支援を表明してきました。 また、紛争鉱物問題に関しても、2012年から準備を進め、2013年8月以来、LBMA(ロンドン貴金属地金市場協会)※2から、「金」に関する紛争鉱物不使用の認証を継続取得し、「銀」について新たに運用を開始しています。さらに、 2014年2月から「錫」に関するRMI※3のRMAP※4認証を毎年取得しています。
- ※1 EITI:Extractive Industries Transparency Initiative 石油・ガス・鉱物資源等の開発に関わる採取産業から資源産出国政府への資金の流れの透明性を高めることを通じて,腐敗や紛争を予防し,成長と貧困削減につながる責任ある資源開発を促進するという多国間協力の枠組み http://eiti. org/
- ※2 LBMA:The London Bullion Market Association 貴金属市場で流通する貴金属地金の品質等を管理する協会 http://www.lbma.org.uk/
- ※3 RMI:Responsible Minerals Initiative 責任ある鉱物イニシアチブ
- ※4 RMAP:Responsible Minerals Assurance Process(旧「Conflict-free Smelter Program」)
三菱マテリアル金属事業カンパニー 責任ある鉱物調達方針(金、銀、錫)
制定:2013年6月19日
最終改訂(改訂9版):2024年10月1日
金属事業カンパニーでは、金、銀及び錫の地金を製造しています。紛争地域等の高リスク地域における、人権侵害、テロリストへの資金供与、マネーロンダリング、不正取引などに係る原料調達は行っておりません。また、原料調達に関して環境及び持続可能性に係る責任に取り組むことの重要性を認識しております。これらの徹底を図るため、金、銀についてはLBMA(London Bullion Market Association)のガイダンスに沿った、錫については“OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”(以下、「OECDガイダンス」)錫、タンタル、およびタングステンに関する補足書に記載のデュー・ディリジェンス・ステップに対してコミットし、RMI (Responsible Mineral Initiative)のRMAP (Responsible Minerals Assurance Process) に沿った管理システムを構築・運用し、定期的に第三者機関による監査を受けることとします。以下に金、銀及び錫に適用する当カンパニーの責任ある鉱物調達方針を示し、実践してまいります。
- 総則
-
- 人権を尊重し、いかなる非人道的行為への直接的・間接的加担をも回避するため、武力紛争または広範な暴力または人々に危害が及ぶその他のリスクが存在するような、紛争地域および高リスク地域における勢力との関係が疑われるような鉱物を使用しません。
“OECDガイダンスAnnexⅡに記載のリスク(下記①~⑥列挙)及び金銀はLBMAガイダンスに記載のリスクについて、リスク管理を行います。(*はLBMAガイダンスにおいてOECDガイダンスとリスクの表現/内容が異なる場合を記載。)- ①非政府武装集団 に対する直接的または間接的支援 (①*非合法な非政府武装集団、または公的もしくは私的な治安部隊に対する直接的または間接的支援)
- ②鉱物の採掘、輸送、取引に関連した人権侵害(②*鉱物の採掘、輸送、取引に関連した系統的又は広範囲な人権侵害)
- ③公的または民間の保安隊に対する直接的または間接的支援(鉱山現場、輸送ルート、サプライチェーンの上流の関係者を違法に管理する組織や、鉱山へのアクセス地点や輸送ルート沿いおよび鉱物の取引拠点において違法な課税や金や鉱物の恐喝を行う組織、または中間業者、輸出企業、国際取引業者に対し違法な課税や恐喝を行う組織、に対する直接的または間接的な支援)
- ④贈収賄および鉱物原産地の詐称
- ⑤資金洗浄 (⑤*資金洗浄またはテロ資金調達)
- ⑥紛争及び高リスク地域(CAHRA)からの鉱物採掘、貿易および輸出に関する政府への税金、手数料及び採掘権料の支払いにおける違反
- ⑦*紛争への加担
- 原料調達に関するリスク管理を行い、取引停止を含めた対応を行います。
- 人権を尊重し、いかなる非人道的行為への直接的・間接的加担をも回避するため、武力紛争または広範な暴力または人々に危害が及ぶその他のリスクが存在するような、紛争地域および高リスク地域における勢力との関係が疑われるような鉱物を使用しません。
- 管理体制と責任
-
- 鉱物管理の主管部署は金属事業カンパニー本社であり、製錬所が独自に調達する原料はありません。
- 当カンパニーが選任するコンプライアンスオフィサーは、関連部署を統括して管理システムを運用するなど、管理マニュアルで定めた権限を有し責任を負います。
- 当カンパニー経営会議は、管理体制全体を統括し、定期的にマネジメントレビューを行うなど、管理マニュアルで定めた権限を有し責任を負います。
- 紛争地域および高リスク地域との関係が疑われる勢力からの原料調達における判断基準及び、LBMAにおけるゼロトレランスのサプライチェーンについて
- 当社が定めた紛争地域および高リスク地域におけるOECDガイダンスAnnexⅡ及びLBMAガイダンスに記載のリスク(1.総則(1)①~⑥、①*~⑦*)の可能性が高いことが判明した場合の金、銀または錫を含む原料の調達、及びESG要因(環境及び持続可能性に係る責任等)のリスクが高いことが判明した、金、銀を含む原料の調達を、高リスクの原料調達と判断します。
なお、LBMAガイダンスの要求事項に従い、以下の場合はゼロトレランスのサプライチェーンとして、直ちに取引を停止致します。- ①世界遺産の地域からの採掘金銀
- ②国際的制裁に違反して調達された採掘金銀・リサイクル金銀
- ③一次サプライヤー/既知の上流企業/その実質的支配者が、既知のマネーロンダリング業者、詐欺師、またはテロリストであるか、重大な人権侵害、または違法な非政府武装集団に対する直接的または間接的な支援への関与が暗黙的に了解される採掘金銀・リサイクル金銀
- 原料購入先に関するデューディリジェンス(以下、「DD」)の実施、及びLBMAにおける高リスクのサプライチェーンについて
- 金、銀を含む原料及び錫を含む原料の全ての購入先についてDDを実施し、リスク評価を行います。リスク評価の結果、高リスクと判断した場合は原料購入の取引の停止/詳細調査(エンハンストデューディリジェンス(以下、「EDD」))等を含む対応を致します。
なお、LBMAガイダンスの要求事項に従い、高リスクのサプライチェーンとして、EDDを実施した結果の対応は以下のように行います。- ①マネーロンダリング、テロ資金供与、深刻な人権侵害、違法な非政府武装集団への直接的または間接的支援、鉱物原産地の詐称の事実があると判断した場合、直ちに取引を停止します。
- ②マネーロンダリング、テロ資金供与、深刻な人権侵害、違法な非政府武装集団への直接的または間接的支援、意図的な鉱物原産地の詐称の疑いがあると判断した場合、ESGに関する甚大な影響がある旨の報告があった場合、一時取引を停止します。
- ③贈収賄、過失による鉱物原産地の虚偽表示、政府に対する税金、手数料及び採掘権料の納付に係る違反、環境、健康、安全、労働及び地域社会に関連する現地法の重大な違反、及び/又は、非常に有害な影響をもたらす可能性が高いESGリスクはあるが、取引先が合理的かつ誠実な努力をしていると結論付けた場合、改善計画に基づく取引継続とします。
- ④「OECDガイダンス AnnexⅡリスク」に抵触する可能性が低い、低リスクのサプライチェーンと判断した場合、カンパニー経営会議へ報告して承認を得た上で、原料購入の取引を継続(または開始)します。
- カンパニー本社購入原料のモニタリング
-
- カンパニー本社で購入した原料は製錬所に供給されます。製錬所では、受入れる全ロットについて、現物確認、鉱量の測定、及び含有成分の分析が行われ、カンパニー本社が事前に提供する購入先提示の情報との整合性の確認を行い、その結果をカンパニー本社へ報告します。
- これら従来から実施してきた原料受入れに関するモニタリングシステムを、カンパニー本社における責任ある鉱物調達の観点からも活用し、鉱物混入の防止システムとして運用することとします。
- 責任ある鉱物調達システムの運用
-
- コンプライアンスオフィサーは、カンパニー本社関連部署及び製錬所に対して、各時点で必要と認められる状況に応じて教育訓練を実施します。
- コンプライアンスオフィサーは、カンパニー本社関連部署及び製錬所に対して、少なくとも1年に一度の頻度でモニタリングを実施します。モニタリングでは責任ある鉱物調達システムに従って適切に業務が遂行されているか、逸脱がないかを評価します。
- 原料調達において、新たな購入先との取引が開始される場合は、その情報がコンプライアンスオフィサーに伝達されるシステムとし、鉱物混入の防止に努めます。
- コンプライアンスオフィサーは、責任ある鉱物調達に関する全ての業務を記録に残し、5年間保存します。また管理マニュアルの文書体系は状況に応じて逐次改訂し、適正に管理するものとします。
以上
LBMA(金、銀)に係わる当社コンプライアンスレポートと、KPMGあずさサステナビリティ社による独立保証報告書(4,072KB)
責任ある鉱物保証プロセス(RMAP)デューデリジェンス報告書(164KB)
金属事業カンパニー(銅、鉛に関する取り組み)
当社金属事業カンパニーで製造する銅地金および鉛地金はLME(ロンドン金属取引所)においてブランド登録されています。今般、LMEが上場ブランドに対して責任ある調達の要件を導入する方針を打ち出したことを受け、金属事業カンパニーでも下記の「責任ある鉱物調達方針(銅、鉛)」を規定し、LMEの調達要件を満たした責任ある鉱物調達を実践しています。
三菱マテリアル(株)金属事業カンパニー 責任ある鉱物調達方針(銅、鉛)
制定:2023年9月1日
金属事業カンパニー製錬事業部直島製錬所、小名浜製錬株式会社小名浜製錬所、細倉金属鉱業株式会社では、銅、鉛の地金を生産しています。これらの地金の原料調達について、London Metal Exchange の Responsible Sourcing 及びCopper Mark の Joint Due Diligence に沿った管理システムを構築・運用し、リスク評価についての独立した第三者評価を受けることとします。
以下に銅地金、鉛地金に適用する当カンパニーの責任ある鉱物調達方針を示し、実践してまいります。
- 銅及び鉛の原料調達について、"OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" Annex I で定義されている 5 段階のデュー・ディリジェンス・プロセスを実施します。
- 原料調達について LME Responsible Sourcing に従い、” OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” Annex Ⅱに記載のリスク(下記列挙)を含む悪影響を及ぼすリスク及び現実化した悪影響に対して、特定、評価、対応するリスク管理を行います。
- ①非政府武装集団に対する直接的または間接的支援
- ②鉱物の採掘、輸送、取引に関連した人権侵害
- ③公的または民間の保安隊への直接的または間接的支援
- ④贈収賄および鉱物原産地の詐称
- ⑤資金洗浄
- ⑥政府への税金、手数料、採掘権料の支払い
- 深刻な人権侵害又は非政府武装集団への加担が判明した場合は直ちに取引停止/契約解除を行います。深刻な人権侵害又は非政府武装集団への加担以外のリスクの場合はリスク緩和を図るとともに、リスク緩和ができないと判断した場合には直ちに取引を停止します。また、リスク管理計画は悪影響を及ぼすリスクおよび現実化した悪影響を管理し緩和するための措置を講じるために実施する手順のフレームワークとして使用し、サプライチェーンの更なる上流に結果的に影響を及ぼす供給業者との関与、事業提携および多様な利害関係者によるイニシアチブ、地方政府および中央政府との関与などを介してリスクを管理し、利害関係者からのフィードバックの回収などで効果追跡できる計画とします。
- 銅及び鉛を含む原料調達サプライチェーンのリスク評価につき、独立した第三者評価を受けるとともに、銅及び鉛を含む原料調達管理の体制及び実施状況について年次報告を行っていきます。
以上
日本新金属(株)(加工事業カンパニー所管)(タングステンに関する取り組み)
当社のタングステン製錬を担当するグループ会社の日本新金属(株)は、2021年6月に従来の「紛争鉱物マネジメント方針」を拡張し、より幅広い地域と鉱物に対象範囲を拡げた「責任ある鉱物調達マネジメント方針」として改訂しました。日本国内でタングステン製錬を行う企業として、製錬工程に投入される原料が「責任ある鉱物調達」ガイドラインに沿った原料であることを確保するとともに、社外のタングステン製錬企業から購入する原料についても、同様の管理を進めています。さらに、2021年11月には、「CFS認証」から発展した「責任ある鉱物保証プロセス(RMAP)」の認証を取得しました。
 日本新金属(株)「責任ある鉱物調達マネジメント方針」
日本新金属(株)「責任ある鉱物調達マネジメント方針」
 日本新金属(株)RMAP認証
日本新金属(株)RMAP認証