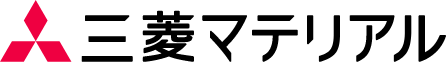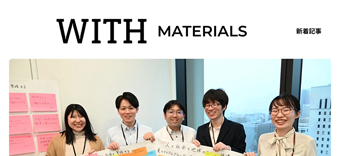Strengthening Measures to Address Global Environmental Issues 地球環境問題対応の強化
生物多様性の確保
生物多様性への配慮
基本的な考え方
生物多様性保全課題については、2019年のIPBES(Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の地球規模評価報告書において自然が世界的に劣化し、自然変化を引き起こす要因が過去50年間で加速していることが科学的な根拠を元に指摘されています。世界は、2022年に生物多様性条約締約国会議(COP15)における「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を受け、2030年に生物多様性の損失を止め反転させる、いわゆるネイチャーポジティブ(自然再興)達成に向けた社会経済活動が企業にも求められています。
当社グループは、行動規範第5章に「生物多様性に配慮して、自然との共生に努めます」と定め、生物多様性への配慮を事業の基本姿勢として社内外に明示しています。環境方針では「天然資源の開発等を含めバリューチェーン全体において生態系に配慮した事業活動を行います」としており、生物多様性問題に関する社会環境の変化を踏まえて当社としての取り組み方針をより具体化することが必要と考えられることから、当該環境方針に基づく詳細な方針として、生物多様性保全方針を制定しています。
生物多様性保全方針
2024年9月24日制定
- 生物多様性保全に取り組む意義
-
三菱マテリアルクループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、「循環をデザインする」というビジョンを掲げ、「持続可能な社会(豊かな社会、循環型社会、脱炭素社会)を実現する」ことをミッションとし、行動規範において「私たちは、環境保全に努め、脱炭素化、資源の有効活用その再資源化に取り組む」ことを私たちが遵守すべきルールとして制定しております。また、サステナビリティ課題(マテリアリティ)として地球環境問題への対応を設定しております。
- 基本理念
-
事業活動において、鉱物や水資源などの天然資源の恩恵を受けていることを認識し、この限られた資源を次世代へとつないでいくために、自然環境への負荷を最小限に抑えた事業活動を行っていきます。
また、わたしたちのルーツである山林・休廃止鉱山や、今後主力施設となっていく再生可能エネルギー発電所などが保持する自然環境を重要な資産として保全し、地域活動も通じて生物多様性保全に関する普及啓発も行っていきます。
これらの活動を通じて、ネイチャーポジティブな社会に貢献するための生物多様性保全への活動を進めていきます。 - 注力領域
-
- 事業活動、原料調達時の生物多様性への影響把握
- 社有林整備、休廃止鉱山管理を通じた生物多様性保全機能の発揮
- 自然と触れ合う場の提供
- 金属資源循環による資源の有効活用と生態系への負荷軽減
- 気候変動対策を通じた生態系保全
- 操業等における環境関連法令遵守
- アプローチ
-
各事業所、社有林、休廃止鉱山などでの生態系、生物多様性の状況把握を実施します。また、サプライチェーンを含めた事業(操業)による生態系への依存や影響を把握して、優先順位付けを行ったうえで適切な対処を行います。
対処にあたっては、自然への影響を与えるものに対して「回避」「低減」「回復・再生」を行うための行動目標を設定し、地域住民や有識者とも協業し、適切なモニタリング体制を構築していきます。
情報の開示
当社グループは、2023年9月に発表されたTNFD※の提言に基づき、の提言に基づき、当社事業の生物多様性に関する依存と影響およびリスクと機会について適切に分析を行い、開示を進めていくことにしています。
2023年度は事業規模の大きい事業所や自然への影響が大きいと考えられる3拠点についてLEAPアプローチに基づく試行的な分析を実施し、2024年度に主要な事業や拠点に関する分析を実施しました。この結果に基づき作成したTNFDレポートを開示しています。今後はこの分析に基づき具体的な対応や目標を取りまとめていくこととしています
- ※ Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)の略。2021年6月設立。
鉱山における生物多様性への取り組み
当社は主原料である銅精鉱を海外鉱山からの輸入に依存しており、安定調達のため海外鉱山への出資を進めていますが、生物多様性への影響が特に顕著なのは、出資先である海外鉱山です。そのため、当社グループでは、法令遵守および “Social License to Operate(社会的営業許可)”という考え方を重視し、各鉱山では、事業活動を行う全ての採掘現場においてレクラメーション(再生)に取り組み、生態系への影響最小化に努めています。各鉱山では、将来の閉山等に向けた対応を円滑かつ適切に行うために、事業活動を行う国・地域の法律や「持続可能な開発のための10原則」等の国際的な取り決めに定められた環境影響評価を実施し、行政、地域住民等のステークホルダーとの対話を通じて、適切な閉山計画の策定を行っています。
当社が出資し、重要な調達先でもある銅鉱山(カッパーマウンテン(カナダ)、エスコンディーダ(チリ)、ロスペランブレス(チリ)、マントベルデ(チリ))では、いずれも採掘事業の開始前に適切な環境影響評価が実施され、開始後も継続的な環境モニタリングが実施されています。また、開発プロジェクトであるサフラナル(ペルー)では2023年5月に環境許認可を取得し、ナモシ(フィジー)においても、環境影響評価のための基礎調査の実施と生物多様性保全のためのデータ収集を行っています。
カッパーマウンテンでは、社会・環境との共生を図る上で社会の期待や環境規制の要件も考慮し、カナダ鉱業協会の持続可能な鉱業に向けた(TSM)イニシアチブの鉱山閉鎖フレームワークとも連携した閉山計画を作成しています。この計画に基づき、生物多様性の保全管理とレクラメーション(再生)に取り組んでおり、環境負荷の最小化に焦点を当て、閉山前にレクラメーション可能な領域を増やしています。具体的には、絶滅危惧種、保護地域、重要生息地等その土地の状況や事業活動による影響度を特定した上で、物理的安定性の向上、水質と水路の保護、土砂保持と侵食制御、土壌の回収と、適切な植生の確保、外来種の排除など、最終的な土地利用とレクラメーションを達成するための戦略を策定し、責任をもって対応しています。これらの戦略は、植生、野生生物、水、水生成分の生物多様性保全を管理する計画、およびレクラメーションの詳細なモニタリング計画とともに、カッパーマウンテンの生物多様性保全管理計画に記載されています。
マントベルデでは、開発プロジェクトを通じて得た生物多様性データを、生物多様性に関する情報共有ネットワークであるGBIF(Global Biodiversity Information Facility)に提出しています。具体的には、グアナコの食餌の研究やキツネの生息範囲の研究、特異種の種子収集と保存等の取り組みを行っています。
当社グループは、出資者として鉱山を運営する事業主体に対し、こうした取り組みが行われることを、事前に確認し、促進しています。また、出資を行っていない鉱山からの調達も、「金属事業カンパニーCSR調達基準」に則り、自然保護区域への配慮や生物多様性の保護がなされていることを確認しています。
製造拠点での取り組み
当社グループの製造事業所でも、各事業所の特性に応じて、生物多様性の保全に取り組んでいます。例えば、直島製錬所(香川県香川郡直島町)では、少雨・乾燥土壌で植物が育ちにくい状況や過去の森林火災などにより山林が一部焼失した経緯から、その植生促進と回復を目指し、年間1ヘクタールの植林活動を実施しています。また、瀬戸内の自然環境を保護するため、所内で排出される排ガスや排水については、国の基準よりも厳しく設定し、処理を徹底しています。
社有林での取り組み
当社は、日本各地に1.3万haの森林を保有し、そこに生息する動植物の生息環境に配慮する森林経営手法を実践しています。動植物のモニタリング活動や、生息を確認した希少種のレッドリスト化も行っています。北海道内の8ヵ所の山林では生物多様性にも配慮した持続可能な森林経営に関する認証を取得しています。今後も、当社グループの事業活動と生物多様性との接点に配慮し、広い視野で保全に取り組んでいきます。
また、当社は2022年4月、環境省が主導する「生物多様性のための30by30(サーティ・バイ・サーティ)アライアンス」(アライアンス)に、参加企業として登録されました。本アライアンスは2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(Nature Positive)国際目標の達成に向けて設立された有志連合です。日本ではこの目標達成に向け、2030年までに自国の陸域・海域の少なくとも30%を保全・保護すること(30by30)の達成を目指し、国立公園等の保護地域の拡充に加え保護地域以外の企業林等で生物多様性保全に資する地域をOECM(Other Effective area-based Conservation Measures)として設定することとしています。環境省はOECMを『自然共生サイト』として認定することとしており、当社の北海道の手稲山林も2023年10月に認定され、認定区域のうち保護地域との重複を除かれた区域が2024年8月にOECMとして国際データベースに登録されましたたました。(TOPICS参照)。
- ※ Other Effective area-based Conservation Measures、公的な保護地域以外の企業林などで生物多様性保全に資する地域

- 「マテリアルの森 手稲山林」 が環境省の「自然共生サイト」認定
~社有林の生物多様性保全が評価~ -
当社社有林「マテリアルの森 手稲山林」(以下、「手稲山林」)が環境省の「自然共生サイト」認定を受けました。
「自然共生サイト」とは民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する区域です。認定区域は保護地域との重複を除き、「OECM※」として国際データベースに登録されます。
- ※ Other Effective area-based Conservation Measures、公的な保護地域以外の企業林などで生物多様性保全に資する地域
当社はこれまで、環境省が主導する「生物多様性のための30by30(サーティ・バイ・サーティ)アライアンス」への参加や、自然共生サイトの認定の仕組み構築を支援する「認定実証事業」にも手稲山林の情報を提供するなど、生物多様性保全に関するさまざまな活動を進めてきました。
このたび認定を受けた手稲山林は、札幌市の市街地に隣接する都市近郊林でありながら、多様な動植物が生息しています。その生物多様性を保全するための森林整備における環境負荷の低い作業システムの採用や、デジタルツールを活用したモニタリング活動などが評価されました。


鉱山における生物多様性への取り組み
銅鉱山(カッパーマウンテン鉱山)での水質モニタリング
当社は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に位置するカッパーマウンテン鉱山に出資し、生物多様性に配慮した企業経営に取り組んでいます。
カッパーマウンテンは、採掘作業から閉鎖まで安全に移行するために、包括的な漸進的レクラメーション利用計画から鉱山計画プロセスを開始します。この計画には、閉鎖の計画、レクラメーションのための適切な資源の割り当て、操業の初期段階における地元の先住民族を含むステークホルダーとの関与などが含まれます。カッパーマウンテンでは、先住民族と協力して、最終的な土地利用の目的を定め、当社の操業の社会的、経済的、環境的、文化的側面に関する基本条件と、鉱山跡地で望ましいレクラメーションや最終土地利用を明確化し、その理解・浸透を図っています。
カッパーマウンテンの漸進的なレクラメーションは、鉱山計画の段階から始まり、鉱山操業の一部として継続的に実施されています。この漸進的なレクラメーションは、2018年に小規模な初期試験で開始され、今後10年間で毎年25ヘクタールのレクラメーションを基本としています。
2023年には、以前にレクラメーションが確認された地域の非経済的岩石貯留地(NERSA)に約77,000本の低木や樹木を植樹しました。
カッパーマウンテンにおけるレクラメーションモニタリング結果を次に示します。
| カッパーマウンテンの漸進的なレクラメーション | |
|---|---|
| 年 | 漸進的なレクラメーション活動 (単位:ha) |
| 2023 | 26.30 |
| 2022 | 20.31 |
| 2021 | 23.97 |
| 2020 | 20.99 |
| 2019 | 7.47 |
また、同鉱山では、同州の水質ガイドラインに従い、鉱山の河川下流での水質モニタリングを行うとともに、鳥類、哺乳類、両生類、水生生物、および生息地等生態系への影響を把握するため、周辺地域の生物多様性の調査を継続的に実施しています。
2019年より上記のウォルフ・クリークの一部を移設してFHOP(魚類生息地再生オフセット・プロジェクト)を開始し、以降、環境モニタリングを継続して実施してきました。この移設された沢の生物の生息域がニジマス等に良好な産卵・飼育環境となっていることが認められています。
 FHOPサイト
FHOPサイト
 ニジマス
ニジマス
銅・金鉱床開発プロジェクトでの環境影響評価
ペルー南部に位置するサフラナル開発プロジェクトでは、EIA※取得の際に実施した環境基礎調査の中で、開発時に想定される環境への影響を最小限に抑制するための調査解析も行っており、動植物の生態系に影響を及ぼす可能性がある場合を想定した新たな生息域の確保等の対策を検討しています。
- ※ Environmental Impact Assessment (環境影響評価)
 探鉱試錐調査
探鉱試錐調査
 河川の水質調査
河川の水質調査
発電所における環境影響評価
安比地熱(株)の事業化における環境影響評価の実施
当社は、2015年に三菱ガス化学(株)と共同で岩手県八幡平市安比高原の西方にて安比地熱(株)を設立し、さらに2018年に電源開発(株)が加わり3社で事業化を推進しています。この事業では、2024年に14,900kWの地熱発電所の運転を開始しています。安比地熱(株)は、2015年に環境影響評価(環境アセスメント)の手続きを開始し、安比地熱発電所の設置により周辺の環境に及ぼす影響について調査、予測および評価を行いました。2018年1月に経済産業大臣より環境影響評価書に対する確定通知を受領し、2019年8月に建設工事を開始しています。
小又川新発電所での自主評価実施
当社は、秋田県北秋田市米代川水系阿仁川支川小又川において、森吉ダム直下に発電所を保有しており、その発電後の放流水を活用する新規水力発電所となる「小又川新発電所(出力10,326kW)」の建設工事を2019年5月に着工しました。新発電所の建設計画では、周辺環境に与える影響について自主環境アセスメントを行うとともに、周辺の河川環境保全のために新たに河川に適した正常流量の放流を計画しています。また、建設工事では、再生可能エネルギーである既存の水力発電所から供給された電力を使用して導水路トンネル(TBM工法)の建設を実施し、建設予定地で伐採された樹木は再資源化する等、環境に配慮した取り組みを実施しています。
インドネシア・カパー・スメルティング社(インドネシア)における生物多様性の保護活動
希少動物保護活動
インドネシア・カパー・スメルティング社は、インドネシアの生物多様性保護に対する継続的な貢献を示すため、2022年から生物保護プログラムの1つであるTaman Safari Indonesiaによる「Komodo Release Program」を共催しています。
コモドオオトカゲは、インドネシア固有の古代のトカゲの1種であり、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されています。
2023年に東ヌサトゥンガラ州の自然生息地に放たれたコモドオオトカゲは6頭います。彼らはサファリパーク保護研究所で飼育され、元の生息地に放たれました。このプログラムの目的は、野生に放した後、GPSを使用してコモドオオトカゲの動きと生態を研究することです。このプログラムは2022年から2027年まで実施される予定です。
 コモドオオトカゲ
コモドオオトカゲ
写真提供:タマンサファリ・インドネシア