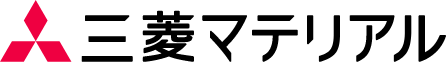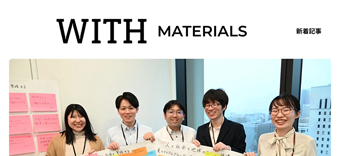- ホーム
- サステナビリティレポート
- 三菱マテリアルのマテリアリティ(重要課題)
- カーボンニュートラル実現に向けた取り組み強化
Strengthening Measures to Address Global Environmental Issues 地球環境問題対応の強化
カーボンニュートラル実現に向けた取り組み強化
気候変動戦略
基本的な考え方
気候変動問題については、2023年のIPCCの第6次統合報告書において人間活動が地球温暖化を引き起こしてきたことを「疑う余地がない」ことと指摘され、GHG※1削減の緊急性が強調されています。世界は、パリ協定のもとで2020年以降の取り組みを進めており、2021年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)におけるグラスゴー気候合意を受け、1.5℃目標、すなわち2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて大きく舵を切っています。
当社グループとしても、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、気候変動問題に真摯に向き合います。国の目標年である2050年度より5年前倒しした2045年度をカーボンニュートラルの目標年として設定するとともに、自社で消費する電力に匹敵する再エネ発電を2050年度には実現し、実質的な再エネ電力自給率100%を目指すなど、「脱炭素社会の実現」に向けた事業活動を進めます。
- ※1 GHG:Greenhouse Gas(温室効果ガス)。
情報の開示
当社グループは、2020年3月、TCFD※2の提言に賛同するとともに、同提言に賛同する企業や金融機関等からなるTCFDコンソーシアムへ参画しました。気候変動が当社事業へ及ぼすリスクと機会およびその分析結果について、TCFD提言に基づき適切に開示を進めていきます。
また、⾮営利団体CDPの質問書に毎年回答しており、A〜D-の8段階のスコアリングにおいて、当社はCDP2024気候変動では初めて最高ランクとなる「A」評価を、CDP2024水セキュリティでは「B」の評価を受けました。また、CDP2024サプライヤーエンゲージメント評価では2年連続で最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に選定されました。詳細は、下記リンクをご覧ください。
- ※2 TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォース)の略。2016年に金融システムの安定化を図る国際的組織の金融安定理事会が設立。


※参考:2023年スコア
ガバナンス
当社は、気候変動問題への対応を含むサステナビリティ課題対応を分掌する執行役(CSuO)を置いています。また、気候変動に関連するリスクと機会への当社グループの戦略的取り組みについては、コーポレート部門に専門部署である「地球環境室」を設置し、当社グループの気候変動対応を企画・推進しています。さらに、地球環境室が事務局を務める「地球環境委員会」では、TCFD提言に基づいたシナリオ分析、気候変動関連リスクおよび機会の評価・管理、GHG削減のための実行計画の策定・管理およびその他気候変動に関する協議、情報共有等を推進しています。これらの取り組みは、戦略経営会議、取締役会に報告され、適切にモニタリングされています。(戦略経営会議・取締役会における審議・報告事項)
- 温室効果ガス削減目標設定および削減計画
- 気候変動関連情報の開示内容
- 各事業における気候変動関連リスク・機会の評価
取締役会ではサステナビリティに関する取り組みのモニタリングに留まらず、異なる視点からサステナビリティへ取り組む方向性を能動的に検討し、社内に示していくことを目的に、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会を設置しました。本委員会は、気候変動関連の当社の取り組みに関するモニタリングおよびその方法、課題について検討し、その内容を取締役会に報告します。

戦略
2021年3月にTCFD提言に基づき、気候変動が当社グループの事業に与える影響(リスクと機会)について把握し、リスクの低減および機会の獲得に向けた対策を検討するため、シナリオ分析を実施しました。
移行リスクと機会については、2023年2月に中期経営戦略2030との整合性を取りながら、シナリオ分析の更新、事業の指標と目標を定めました。1.5℃シナリオと4℃シナリオを設定し、気候変動に対する政策および法規制が強化され、炭素価格制度(カーボンプライシング)が導入、強化された場合の当社グループへの財務影響を試算しました。また、EV需要変化やエネルギー利用形態の変化、循環型社会への移行によるリサイクル事業の需要変化について、当社の事業への影響をリスクと機会の側面から分析しました。物理的リスクについても、気候変動に関連すると考えられる激甚化した豪雨・洪水や高潮・渇水等の急性および慢性リスクによる被害等の水リスクを含め、全社リスクマネジメント活動において管理しています。
シナリオ分析結果の詳細は「気候変動に関するリスクと機会」をご参照ください。
また、2024年度より、社内におけるGHG排出量に係る意識向上および脱炭素への取り組みを推進するため、ICP制度を導入しています。
リスクマネジメント
当社グループでは、気候変動に関するシナリオ分析の結果、気候変動に関するリスクを当社グループの業績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がある主要なリスクのひとつとして認識し、当社グループのリスクマネジメント活動の中で取り組みを進めています。
リスク対策の実施状況は、SCQ推進本部、戦略経営会議で協議し、モニタリングしています。
これらの会議体では、CSuOが実行責任を担い、監査委員会からも独立して運営しています。また、取締役会では、リスクマネジメントプロセスの実効性について検証、見直しを実施し、リスクマネジメントを総合的に監督しています。
当社グループのリスクマネジメント体制および運用状況、重大リスクの選定プロセス等の詳細は「グループガバナンスによる内部統制の拡充」をご参照ください。
指標と目標
当社グループは、GHG排出量(Scope1 + Scope2)の削減目標を、資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除いた排出量に対して設定する見直しを行いました。
2022年に改正されたエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」)および地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」)の運用変更に基づく定期報告が2024年度から開始されたことに伴い、当社の両法令に基づくGHG排出を再整理し、これまで算定・報告の対象外であったE-Scrapに含まれるプラスチックの燃焼に伴い生じるCO2や製造工程で使用する石灰石の化学反応に伴い生じるCO2等のGHG排出量を法令報告の対象に追加しました※3。
当社は「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを私たちの目指す姿に掲げ、当社事業の強みを活かして資源の循環を強化していくことを中期経営戦略の柱としていることから、新たなGHG削減目標を、資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除いたGHG排出量※4を対象に、2030年度までに2020年度比で47%削減※5することにしました。なお、本目標の見直しに伴い、2024年11月にSBT認定を取り下げました。
- ※3 当社のGHG排出量は、温対法の運用変更前の報告書と比べて削減目標の基準年度としている2020年度で約23万t、削減目標年度の2030年度で約35万t増加します。
- ※4 温対法に基づく調整後排出量の算定方法によります。
- ※5 従来の目標である45%削減(E-Scrap由来および石灰石等由来の排出を除いたもの)と同水準です。E-Scrap由来および石灰石等由来の排出を含めた場合(温対法に基づく基礎排出量の場合)には29%削減に相当します。
GHG排出量の削減目標に加え、当社グループが強みを有する地熱発電等の再生可能エネルギーの開発や利用拡大を進め、使用電力の再生可能エネルギー利用率を2035年度に100%とすること、および電力の再生可能エネルギーの自給率を2050年度までに100%にする目標も定めています。
これらの目標の達成に向け、2030年度までに主に製造拠点の省エネ対策や設備改善等へ105億円、再生可能エネルギー事業へ300億円の投資を実行していきます。
製造現場における省エネルギーや化石燃料の使用量削減に加え、カーボンニュートラル(以下、「CN」)社会に貢献する製品やCO2回収・処理等の技術の開発を進めるとともに適用可能な技術を活用し、資源循環の取り組みにより排出されるGHGを含めて2045年度のカーボンニュートラルの達成を目指します。
2050年のCN社会達成のためには、当社事業のサプライチェーンのGHG排出量削減が不可欠であるとの観点から、Scope3(Scope1およびScope2以外の事業活動に関連する他社の排出)についても2030年までに2020年度比で22%以上削減する目標を設定しています(削減目標の対象はカテゴリ1、3および15)。
GHG排出量削減目標
CNに向けたロードマップ
日本鉱業協会カーボンニュートラル計画への参画
当社が所属する日本鉱業協会は、地球温暖化問題の解決に向け、1997年に京都議定書の採択に先駆けて「環境自主行動計画」を策定し、2013年からはさらに発展した「低炭素社会実行計画」を策定して、非鉄製錬における国内のCO2排出量削減に努めてきました。なお、政府が2050 年カーボンニュートラルおよび2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減とする目標(産業部門の目標は38%削減)を掲げ、カーボンニュートラルの実現に向けた関心と期待が高まったことから、2021年度に「低炭素社会実行計画」を「カーボンニュートラル行動計画」に改めています。
取り組みの結果、2020年度には、2030年度の目標として掲げていたCO2排出原単位1990年度比26%削減をほぼ達成できる状況であったことから、産業構造審議会から目標見直しの助言を受けて、2022年に目標の見直しを行っています。
- a. 目標の前提
-
- 2030年の生産量を 280.0 万tとする。(2022年度 240.7 万t)
- 目標指標をCO2排出量、基準年度を2013年度とする。
- 電力CO2排出係数(kg-CO2/kWh)を調整後排出係数(受電端)とする。
- b. 目標
-
- 2030年度におけるCO2排出量を2013年度比で、38%削減する。
日本鉱業協会のCO2削減目標は、日本国政府が掲げる目標と整合しているため、当社は、今後も同協会の削減に向けた取り組みへの参画を継続します。
執行役(CEOを除く)の年次賞与(短期インセンティブ報酬)における非財務評価項目の内容(2024年度)
各執行役は、非財務評価項目として3つの目標を設定し、そのうち1項目はサステナビリティ課題とするよう義務付けています。これら3つの目標は、さらに2~3個の小項目に細分化され、それぞれの項目について目標を設定しています。以下の表は、2024年度の目標として設定している非財務評価項目の内容を、サステナビリティ基本方針等に基づいて分類したものです。なお、2024年度は、気候変動パフォーマンスが含まれる「地球環境保全への積極的取り組み」に関して、5名の執行役が目標を設定しています。
| サステナビリティ基本方針に沿った項目 | 執行役 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 安全と健康最優先の労働環境整備 | 〇 | 〇 | |||||
| 人権尊重 | 〇 | ||||||
| ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ステークホルダーとの共存共栄 | |||||||
| ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 公正・適正な取引と責任ある調達 | 〇 | 〇 | |||||
| 安心・安全・高付加価値な製品の安定的提供 | |||||||
| 地球環境保全への積極的取り組み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
サステナブルファイナンス
当社は、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速するため、2023年11月にトランジション・リンク・ファイナンス・フレームワークを策定(2024年8月にGHG排出量の削減目標設定変更に伴い改定)し、フレームワークに基づくトランジション・リンク・ボンドの発行およびトランジション・リンク・ローンの実行を行っています。
当社は、調達した資金を活用し、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速していきます。
詳細は、「サステナブルファイナンス」 をご参照ください。
カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products、以下「CFP」)に関する取り組みの方向性について
CFP※6の算定については、国内外において政府や業界団体など多方面で算定方法や活用方法について検討が行われており、取り組みへの関心が高まっています。
そのような状況のもと、以下の方向性に沿って、今後当社におけるCFPの取り組みを推進していきます。
展開
当社の製造する主たる製品においてCFPの算定を順次進めます。
データ信頼性確保に向けた仕組みの構築に着手します。
検証・開示
CFPの算定が完了した製品について、必要に応じ、第三者機関による検証、開示を進めます。
削減
当社のGHG削減施策を計画的に実施し、CFPの削減を図ります。
サプライヤーとのエンゲージメントを進め、上流から下流までの一貫したGHG削減への取り組みを推進します。
取り組み実績
- ※6 製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の算定・表示。
インターナルカーボンプライシング(ICP)制度の導入
当社は、2024年4月から社内におけるGHG排出量に係る意識向上および脱炭素への取り組みをより推進するため、社内で独自にGHG排出量に対して仮想的に価格を設定し、投資判断に活用するインターナルカーボンプライシング(ICP)制度を導入しています。
社内炭素価格を1万円/t-CO2eと設定し、自社のGHG排出量(Scope1 + 2)に削減貢献のある設備投資を対象として投資判断に利用しています。ICP制度の導入により脱炭素に寄与する投資を促進することでGHG排出量の削減を積極的に推進します。
気候変動に関するリスクと機会
当社グループへの財務影響としては、気候変動に対する政策および法規制が強化され炭素価格制度(排出権取引制度や炭素税)が導入、強化された場合等、GHG排出量に応じて追加費用が発生します。また、脱炭素社会への移行に伴い、当社における従来からの製品市場において縮小が見込まれる分野も存在しており、新たな市場拡大分野への対応が遅れた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。今、世界はパリ協定に基づき急速にカーボンニュートラルの社会へ移行する動きが高まっています。当社は、このような社会環境の変化に対して迅速に対応し、新たな価値を提供していく必要があると考えています。
具体的には、GHG削減目標を設定し、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの使用を拡大することにより、当社グループの事業活動により排出されるGHGを着実に削減していきます。さらに、当社グループ製品の市場競争力を向上するため、製造プロセスの改善や環境配慮型製品の開発を推進しています。
物理的リスクについては、気候変動に関連すると考えられる激甚化した豪雨・洪水や高潮・渇水等の急性および慢性リスクによる被害等の水リスクを含め、全社リスクマネジメント活動において管理しています。
また、気候変動に関する機会については、気候変動に関する政策等の強化により、省エネ・GHG排出削減に貢献する技術や製品・サービスの需要が拡大すると想定しています。当社グループは、脱炭素化に貢献する素材・製品の製造、非鉄金属資源リサイクル、地熱発電等の再生可能エネルギーの開発・利用促進、CO2回収・有効利用に関する技術開発、保有する山林の保全活動等に取り組むことで、経済的価値と社会的価値の両立を目指していきます。
シナリオ分析
当社グループは、2021年3月、気候変動が当社グループの事業に与える影響(リスクと機会)について把握し、リスクの低減および機会の獲得に向けた対策を検討するため、シナリオを設定し、その分析を実施しました。移行リスクと機会については、2023年2月に中期経営戦略2030との整合性を取りながら、1.5℃シナリオおよび4℃シナリオを設定した分析、指標・目標の設定を行いました。今後は、この指標・目標に基づいたモニタリングを実施していくことにしています。物理的リスクについては、現在分析の更新および指標・目標の検討を進めています。
リスク・機会およびその対策の特定プロセス
リスク・機会の抽出 |
事業に関連する気候変動リスク・機会として、移行リスク・機会と物理リスクを抽出 |
|---|---|
| 重要リスク・機会 要素の特定  |
抽出したリスク・機会について、事業へのインパクトや事業戦略との関連性、ステークホルダーからの関心度合い等を勘案し、重要度の高いリスク・機会要素を特定 |
事業への影響を分析 |
重要リスク・機会について事業への影響度を分析 分析・評価では、1.5℃シナリオと4℃シナリオを使用
|
| 対策および指標・目標の検討 | リスクの低減、機会獲得に向けた対策を検討 モニタリングする指標・目標(GHG排出削減目標等)を設定 |
シナリオ分析 – 想定する2030年~2050年の世界
分析で想定する世界
| 1.5℃シナリオ(2050年CNに向けた世界) | 4℃シナリオ(現行・成り行きの世界) |
|---|---|
| 世界のエネルギー部門が2050年までにCO2排出量を正味ゼロにするために、達成可能な道筋を設定したシナリオ。今世紀末までの世界の平均気温の上昇を1.5℃未満に抑えるために脱炭素社会に向けた社会変化が、事業に影響を及ぼす世界を想定。 | 現在実施されている特定の政策や、世界中の政府が発表した政策を、国あるいはセクターごとに評価し、現在の政策設定を反映させたシナリオ。目標達成を必須とせず、今世紀末までの世界の平均気温が4℃程度上昇する世界を想定。 |
|
|
TCFD提言に基づく当社のシナリオ分析の概要
気候変動のリスク・機会のうち移行リスクと機会について、全事業共通で1テーマ、3つの大テーマについて事業ごとに計9テーマのシナリオ分析を実施しました。分析に際して使用する外部データおよび内部データを更新しました。
炭素税負担・エネルギーコスト等の変化(全事業共通)
【1.5℃】リスク要素:炭素価格税制度の導入・強化(操業コスト増加)/
【4℃】リスク要素:炭素価格税制度の導入
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】炭素価格制度の導入・強化による生産コストの増加
- GHG排出量に対する課税強化、電力価格上昇によるエネルギーコスト増加
- グリーン電力証書の調達額や排出権取引コストが増加
- 脱炭素の進展により化石燃料単価は減少
【4℃】炭素価格制度の導入・燃料単価増による生産コストの増加
- 脱炭素が現状の政策以上の進展を見せず、化石燃料の需要は2030年まで増加するため、燃料単価は増加
- カーボンプライス単価は緩やかに上昇
- 影響分析
-
【1.5℃】当社グループのGHG排出量目標を達成した場合、2030年度CP負担額は約166億円、エネルギーコストの2020年度からの増加額は71億円と試算された。
炭素価格は、当社のコストの増加要因になる。炭素価格の影響は社会全体にも及ぶが、GHG排出量削減の遅れや当社の製品価格への転嫁が進まない場合は収益低下になるリスクとなる。【4℃】当社グループのGHG排出量目標を達成した場合、2030年度CP負担額は約83億円、エネルギーコストの2020年度からの増加額は75億円と試算された。
1.5℃シナリオと比べて炭素価格による影響は小さいが、燃料単価の上昇によるエネルギーコストの増加と併せて当社の生産コストの増加要因になる。
- 指標
- 当社グループGHG排出量
(Scope1 + 2) - 目標
-
- 2030年度 47%削減(2020年度比)
(資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除く) - 2045年度 カーボンニュートラル
(資源循環の取り組みにより排出されるGHGも含む)
- 2030年度 47%削減(2020年度比)
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 2030年度までのGHG排出量削減計画を策定し、設備や工程の高効率化等によるエネルギー使用量削減、プロセスの電化や燃料転換、再生可能エネルギー(再エネ)由来電力への切り替えを進める
- 2035年度までに当社グループの使用電力の100%を再エネ由来電力に切り替える
- 長期的にCN燃料の利用やCO2の回収・利活用などの革新的技術開発を加速する
目標に対する2023年度実績
当社グループGHG排出量(Scope1,2)
温室効果ガス総排出量(Scope1 + Scope2)は、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めた結果、2022年度比2%減の887千t-CO2e★でした。

- ※ 資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除く。
- ※ 2023年度までに事業譲渡等により連結対象から外れた、または外れることが決定した事業および子会社を除く。
気候変動への対応進展による銅の需要の変化(製錬・資源循環事業)
【1.5℃】機会要素:xEV販売台数の増加/
【4℃】機会要素:自動車販売台数の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】脱炭素化に向けたEV販売台数の増加による急速な銅需要の拡大
- 2030年度に向けて自動車全体の販売台数が増加、世界の自動車向け銅必要量は、2020年度比で2030年度に約3.3倍、2050年度に約4.6倍に拡大
- 2030年度の世界のxEV販売台数は、2020年度比で約24倍に増加と予測
【4℃】xEV比率は低いものの総自動車販売台数の増加により銅需要は増加
- xEV比率が低いものの自動車全体の販売台数は増加するため、世界の自動車向け銅必要量は、2020年度比で2030年度に約2.1倍、2050年度に約2.7倍に拡大
- 2030年度の世界の総自動車販売台数は、2020年度比で約1.8倍に増加と予測
- 影響分析
-
1.5℃シナリオでは銅使用量のより多いxEVの販売台数の大幅な増加により、4℃シナリオでは総自動車販売台数の増加により、世界の自動車向け銅需要が大幅に増加することが予測される。当社の電気銅生産能力の増強によって需要を取りこむことで、売上の拡大につながる機会となる。
- 指標
- 電気銅販売量
- 目標
- 2030年度末
83万t /年
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
- 拡大する銅需要に対応するため、国内拠点での設備投資を行い、2030年度時点での銅精鉱の処理量を現状比1.3倍(直島)、電気銅販売量を1.4倍(全社)に増強し、電気銅の安定供給によって脱炭素社会の実現に貢献する
目標に対する2023年度実績
電気銅販売量
2023年度の電気銅販売量は、小名浜製錬所の完全子会社化により増加して、65万tとなりました。

自動車リサイクルに関わる需要の変化(製錬・資源循環事業)
【1.5℃, 4℃】リスク要素:日本の廃車発生台数の減少
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】国内の人口減、脱炭素社会によるカーシェアリングの進展による廃車発生台数の減少
- 日本国内の人口減少およびカーシェアリングの進展による販売台数減少に伴い、日本の自動車廃車発生台数は、2020年度比で2030年度にほぼ横ばい、2050年度に約0.85倍に減少
- 日本国内の自動車全体の処理台数は減少するが、次世代自動車の比率は増加する(2030年度18%、2050年度78%)
【4℃】国内の人口減による廃車発生台数の減少
- 日本国内の人口減少による販売台数減少に伴い、日本の自動車廃車発生台数は、2020年度比で2030年度にほぼ横ばい、2050年度に約0.89倍に減少
- 影響分析
- 1.5℃、4℃シナリオとも、国内の自動車処理台数は減少すると見込まれ、自動車リサイクルの売上が減少するリスクがある。ただし、1.5℃シナリオでは有価金属価格の高騰により市場規模の縮小傾向は緩和される。
- 指標
- 自動車リサイクル年間処理台数
- 目標
- 2030年度末
700百台 /年
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 家電リサイクル事業で蓄積した技術を活かす次世代自動車の効率的処理技術を強みとしてシェアを拡大することにより、売り上げの拡大を目指す
- 次世代自動車リサイクルの処理拠点として、現状の技術実証でのアライアンス等を活用して拠点増強を行い、全3拠点体制にすることで処理能力を増強する
- 自動車リサイクルにより資源リサイクルのニーズに応え、循環型社会の実現に貢献する
目標に対する2023年度実績
自動車リサイクル年間処理台数
2023年度の自動車年間処理台数は、中古車の価格高騰や販売店からの入庫減少などの影響が続き、2022年度と同水準の91百台となりました。

EVシフトによる製品需要の変化(銅加工事業)
【1.5℃】機会要素:xEV販売台数の増加/
【4℃】機会要素:自動車販売台数の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】脱炭素化に向けたEV関連製品の急速な需要拡大
- 2030年度に向けて自動車全体の販売台数が増加、自動車向けコネクター・バスバー需要は、2020年度比で2030年度に約2.6倍、2050年度に約3.1倍に拡大
- xEVの2030年度の販売台数は、2020年度比で約24倍に増加と予測
【4℃】xEV比率は低いものの総自動車販売台数の増加により製品需要は増加
- xEV比率が低いものの自動車全体の販売台数は増加するため、自動車向けコネクター・バスバー需要の拡大は、2020年度比で2030年度に約2.2倍、2050年度に約2.4倍程度
- 2030年度の総自動車販売台数は、2020年度比で約1.8倍に増加と予測
- 影響分析
-
1.5℃シナリオでは銅製品の使用量がより多いxEVの販売台数の大幅な増加により、4℃シナリオでは総自動車販売台数の増加により、当社の銅圧延製品等の大幅な需要拡大が予測される。関連製品の生産体制強化により需要を取りこむことで、売上の拡大に繋がる機会となる。
- 指標
- 車載用純銅条販売量
- 目標
- 2030年度末
2倍(2020年度比)
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 急拡大するEV向け製品需要に応えられる供給体制を構築するため、2030年度時点での銅部材の生産能力を2020年度比1.3倍以上に増強する(国内生産拠点で生産能力増強中)
- より高性能で環境負荷の低い製品の開発により、脱炭素社会の実現に貢献する
目標に対する2023年度実績
車載用純銅条販売量
2023年度の車載用純銅条販売量は、自動車メーカーの電動車両生産の増加に伴い、車載部品メーカー向け電池・電子機器用のバスバーが増加したことおよび大型化したことにより、2022年度より2.5%増加しました。

モーダルシフト、EVシフトに関わる需要の変化(加工事業)
【1.5℃】リスク要素:モーダルシフト等に伴う加工製品市場の急変/
【4℃】機会要素:エンジン搭載車・航空機の生産台数増
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】EV比率の増加によるエンジン向け切削工具の需要減少
- xEV販売台数の著しい増加、軽量化素材の利用率の増加
- エンジン搭載車の生産台数は、2020年度比で2030年度に約0.59倍、2050年度に約0.01倍に減少が見込まれ、エンジンやトランスミッション加工用の切削工具の売上は減少
- 航空機の生産台数は2020年度比で2030年度に約1.18倍、2050年度に約1.61倍に増加が見込まれ、航空機部品加工用の切削工具の売上が増加
【4℃】エンジン搭載車・航空機の生産数の増加による切削工具の需要増加
- エンジン搭載車の生産台数は、2020年度比で2030年度に約1.44倍、2050年度に約1.32倍に増加が見込まれ、エンジンやトランスミッション加工用の切削工具の売上が増加
- 航空機の生産台数は、2020年度比で2030年度に約1.48倍、2050年度に約2.60倍に増加が見込まれ、航空機部品加工用の切削工具の売上が増加
- 影響分析
-
【1.5℃】自動車産業では電動/軽量化への動きが加速し、難削材加工用の切削工具の需要増加が予測されることから、製品構成を見直し、需要を取り込むことで売上が拡大する機会となる可能性がある。一方、現在の主力製品であるエンジンやトランスミッション加工用の切削工具の売上は減少し、2020年度比で2030年度には0.996倍、2050年度には0.718倍にまで減少するリスクがある。
航空宇宙産業では航空機の生産数増加が予測されることから、同産業向け切削工具の売上は2020年度比で2030年度に1.18倍、2050年度に1.61倍の増加を見込んでいる。【4℃】モーダルシフト、EVシフトが進まず、エンジン搭載車や航空機の生産数は増加が予測されることから、主力製品である自動車産業および航空宇宙産業向け切削工具の売上が増加する機会となる。売上高は、2020年度比で、自動車産業向け切削工具では2030年度には1.71倍、2050年度には1.65倍、航空宇宙産業向け切削工具では2030年度には1.48倍、2050年度には2.60倍にまでそれぞれ増加を見込んでいる。
- 指標
- 切削工具売上高
- 目標
- 2030年度末
2.3倍(2020年度比)
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 難削材加工用工具等、1.5℃シナリオの世界に向けて拡大する需要に応える製品を開発・供給しグローバルシェアを拡大するとともに、脱炭素社会の実現に貢献する
- 自動車向け製品市場は、EV化の動向を注視し、必要に応じてEV部品加工用工具を開発していく。また、自動車産業に代わる新たな市場として、小型精密加工分野(ロボット、半導体製造装置、通信等)を戦略市場とし切削工具の売上増加を目指す
目標に対する2023年度実績
切削工具売上高
2023年度の切削工具の売上高は、国内や中国の需要回復の遅れにより、2022年度から2.5%の増加に留まりました。

LIB-R,PV-Rに関わる需要の変化(製錬・資源循環事業)
【1.5℃, 4℃】機会要素:車載用LIB、太陽光パネル(PV)リサイクル需要の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】EV、太陽光発電の急激な需要拡大による車載用LIB、PVの排出に伴うリサイクル需要の拡大
- xEVの廃車に伴い発生する日本国内のLIBのリサイクル量(リユースを考慮)は、2020年度比で2030年度に約50倍、2050年度に350倍以上に拡大すると予測
- 日本国内のPVのリサイクル量(リユースを考慮)は、2020年度比で2030年度に約8.3倍、2050年度に300倍以上に増加すると予測
【4℃】EV、太陽光発電の需要増による車載用LIB、PVの排出に伴うリサイクル需要の拡大
- xEVの廃車に伴い発生する日本国内のLIBのリサイクル量(リユースを考慮)は、2020年度比で2030年度に約14倍、2050年度に92倍に拡大すると予測
- 日本国内のPVのリサイクル量(リユースを考慮)は2020年度比で2030年度に約7.8倍、2050年度に120倍以上に増加すると予測
- 影響分析
-
1.5℃、4℃シナリオとも、 EV需要拡大、太陽光発電の需要拡大により、今後日本国内の車載用LIBやPVの排出量が増加し、それに伴いリサイクル需要も増加することが予測される。現在進めている実証試験に基づき事業化を進めることで、売上の拡大につながる機会となる。
- 指標
- 車載用LIBリサイクル※7処理量
- 目標
- 2030年度末
870t-LIB/年
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 家電リサイクル拠点における対象品目の拡張に向けてPVリサイクルの事業化を進める
- 各地域における自動車リサイクル/LIBリサイクル拠点の整備およびリサイクル技術の高度化・効率化に取り組み、循環型社会の実現に貢献する
- ※7 ブラックマス化(LIB取り出し、放電、解体、熱分解、破砕選別)まで。
目標に対する2023年度実績
LIBリサイクル技術の開発状況
ロボットを活用したLIBユニットの解体自動化など、引き続き、LIB解体処理およびブラックマス化の事業基盤構築に向けた技術開発を進めています。今後、廃棄量が増大する車載用LIBを安全かつ効率的に、適正処理する技術を確立することで、循環型社会の実現に貢献できるよう検討を進めていきます。
バッテリーに関わる需要の変化(加工事業)
【1.5℃, 4℃】機会要素:EVバッテリー、蓄電池需要の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】EVバッテリー、定置用蓄電池の急激な増加によるタングステン粉末の需要の拡大
- BEVおよびPHEVの販売台数の増加により、EVバッテリー需要は、2020年度比で2030年度に約21倍、2050年度に約30倍に拡大すると予測
- 再生可能エネルギーの需要拡大に伴う定置用蓄電池の増設量は、2020年度比で2030年度に約20倍、2050年度に約22倍に増加すると予測
【4℃】EVバッテリー、定置用蓄電池の増加によるタングステン粉末の需要の拡大
- BEVおよびPHEVの販売台数の増加により、EVバッテリー需要は、2020年度比で2030年度に約6.7倍、2050年度に約12倍に拡大すると予測
- 再生可能エネルギーの需要拡大に伴う定置用蓄電池の増設量は、2020年度比で2030年度に約5.2倍、2050年度に約10倍に増加すると予測
- 影響分析
-
1.5℃シナリオではEV需要の拡大、蓄電池需要の急激な増加により、二次電池用高機能粉末の需要が大幅に増加することが予測される。4℃シナリオにおいても、程度は小さいがEV需要、蓄電池需要が増加する。いずれのシナリオにおいても、当社のタングステンを主体とする高機能粉末の製造能力の増強により需要を取りこむことで売上増加の機会となる。高機能粉末の売上は当社の製造計画の達成により、2020年度比で2030年度に1.9倍、2050年度に3.8倍の増加を見込んでいる。
- 指標
- 二次電池用高機能粉末製造量
- 目標
- 2030年度末
1.9倍(2020年度比)
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- EV用LIB、太陽光発電設備用LIBのタングステン粉末製品等、1.5℃シナリオの世界に向けて拡大する需要に応える製品を開発・供給し、脱炭素社会の実現に貢献する
- タングステン粉末製品はマサンハイテック社との協業により事業拡大を行う
- タングステンリサイクルの推進により循環型社会の実現に貢献する
目標に対する2023年度実績
二次電池用高機能粉末製造量
2023年度の二次電池用高機能粉末製造量は、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準にまで回復しましたが、二次電池市場の拡大鈍化により2022年度から2.9%の増加に留まりました。

再エネの需要の変化(再生可能エネルギー事業)
【1.5℃, 4℃】機会要素:再生可能エネルギーの普及・需要の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】ネットゼロ社会に向けた、再生可能エネルギー市場の中長期的拡大
- 再生可能エネルギーの需要は今後ますます伸び、日本の地熱発電および風力発電の発電量はそれぞれ、2020年度比で2030年度に4.7倍、9.8倍、2050年度に15倍、48倍に増加すると予測
- 再エネの普及状況、需給関係により、環境価値は0.3円~4円/kWh、FIT, FIPの単価低下率を10%/3年と設定
【4℃】現在の政策の実現により再生可能エネルギー需要は拡大するが限定的
- 再生可能エネルギーの需要は伸び、日本の地熱発電および風力発電の発電量はそれぞれ、2020年度比で2030年度に2.3倍、5.0倍、2050年度に4.0倍、7.5倍に増加すると予測
- 再エネの需要は限定的と考え、環境価値は0.3円、需要促進のためFIT, FIPの単価低下率は5%/3年と設定
- 影響分析
-
売電単価や環境価値は環境政策や技術の進展により変動する一方、1.5℃、4℃シナリオとも再生可能エネルギー需要自体は拡大し、特に風力発電、地熱発電の需要の伸び率は他の再エネ電源と比較して高い。新規発電サイトの調査・開発を行うことで当社の再生可能エネルギー事業拡大の機会となる。当社持分発電量の計画達成により、売上は1.5℃シナリオでは2020年度より2030年度に5,240百万円、2050年度には23,668百万円増加、4℃シナリオでは2020年度より2030年度に5,046百万円、2050年度には20,185百万円増加する。
- 指標
- 再生可能エネルギーの
当社持分売電量 - 目標
- 2030年度末
575GWh
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 既存発電所の安定操業と環境価値の活用などにより収益力向上に取り組む
- 新規発電サイトの調査・開発(八幡平地区およびその他の地域での新規地熱事業の展開、風力発電への参入)に注力する
- 他社との協業による発電事業および関連事業規模の拡大を目指す
目標に対する2023年度実績
再生可能エネルギーの当社持分売電量
2022年12月の小又川新発電所の営業運転開始および2024年3月の安比地熱発電所の営業運転開始により、2023年度は前年度比107%の発電量を達成しました。

- ※ 持分買電量として各発電所の送出電力量を積算している。
- ※ 2020~2022年度に小又川新発電所の工事のため当社内で消費した電力を含む。
循環型社会への移行によるE-Scrapリサイクル事業の需要の変化(製錬・資源循環事業)
【1.5℃, 4℃】機会要素: E-Scrapリサイクルの需要の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】各国の経済成長に伴う廃電子機器リサイクル需要の増加
- 持続可能な社会の構築に向け比較的順調な世界であり、世界的な経済の不平等が解消され、世界経済が成長することでE-Scrap発生量は増加すると想定
- 世界のE-Scrapの推計発生量は、地域別のGDP成長率、地域別の人口推移より、2020年度比で2030年度に1.4倍、2050年度に2.5倍と試算
(※2022年度分析実施時の試算結果) - E-Scrap中の有価金属の品位の低下により回収量が減少するリスクがあるが、当社のE-Scrap処理量24万t達成時の有価金属回収量は2020年度比で1.9倍
【4℃】各国の経済成長に伴う廃電子機器リサイクル需要の増加
- 化石燃料依存の解消があまり進まず経済成長のスピードが遅い世界であるが、世界全体での人口増によりE-Scrap発生量は増加すると想定
- 世界のE-Scrapの推計発生量は、地域別のGDP成長率、地域別の人口推移より、2020年度比で2030年度に1.3倍、2050年度に1.6倍と試算
(※2022年度分析実施時の試算結果)
- 影響分析
-
1.5℃シナリオでは各国の経済成長と世界全体での人口増、4℃シナリオでは世界全体での人口増により、2030年度における世界のE-Scrap発生量は増加する。E-Scrap中の有価金属の品位の低下による回収量の減少、銅需要の高まりによる競合他社によるE-Scrap市場への相次ぐ参入や国際的な資源囲い込みの動きによってE-Scrapの集荷が困難になるリスクがあるが、当社のリサイクル処理能力を増強することにより、当社のE-Scrap処理量が増加し、売上増加の機会となる。
- 指標
- E-Scrap類処理能力
- 目標
- 2030年度末
24万t/年
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- E-Scrap発生量増加に伴うリサイクル需要増加に対応するため、リサイクルヤードの建設、E-Scrap中の微量元素を効率的に回収する体制の強化等により、E-Scrap類の処理能力を増強する
- E-Scrap取引用プラットフォームMEX(Mitsubishi Materials E-Scrap EXchange)の機能強化により、顧客利便性の向上、E-Scrap類の集荷増につなげ、循環型社会の実現に貢献する
目標に対する2023年度実績
E-Scrap類処理能力
2023年度のE-Scrap類処理能力は、2020年度から変化はなく16万tです。2030年度の目標値24万t達成に向け、2023年度に小名浜製錬所で新リサイクルヤードを建設し、受け入れ能力が増加しました。2026年度に直島製錬所での増処理工事を実施する予定です。

家電リサイクルに関わる需要の変化(製錬・資源循環事業)
【1.5℃, 4℃】機会要素:家電リサイクル需要の増加
- 想定する世界と事業影響
-
【1.5℃】温暖化・エネルギーコスト上昇による省エネ家電への買い替え頻度の増加による廃家電処理重量の増加
- 2030年度は日本の人口は減少するものの、世帯人員の減少により世帯数は増加することで家電保有量はわずかに増加するが、2050年度にはさらに人口減少が進むことにより世帯数も減少し家電保有量は減少。
- 低炭素規制や燃料価格の上昇により省エネ指向が高まり、上位品目への買い替え頻度が増加。
- リサイクル規制等により、家電回収率は2050年度に向けて増加。
【4℃】気温上昇によるエアコン保有量の増加、故障による買い替え頻度の増加による廃家電処理重量の微増
- 1.5℃よりも出生率が低く、さらに日本の人口、世帯数が減少することで、家電保有量は減少
- エアコンは気温上昇による故障での買い替え頻度が増加。
- 風水災の増加による家電の買い替え頻度が増加。日本全体の廃家電処理重量は、2030年度、2050年度ともに2020年度からわずかに増加する。
- 影響分析
-
【1.5℃】日本の世帯数の変化による家電保有量の増減、リサイクル規制等による家電回収率の増加により、日本全体の廃家電処理重量は、2020年度比で2030年度に6%、2050年度に10%増加すると試算される。当社の家電処理事業の規模を拡大することにより、売上が増加する機会となる。
【4℃】気温上昇によるエアコン保有量の増加、故障や風水災による買い替え頻度の増加により、日本全体の廃家電処理重量は、2020年度比で2030年度に2%、2050年度に1%増加すると試算される。当社の家電処理事業の規模を拡大することにより、売上が増加する機会となる。
- 指標
- 家電リサイクル年間処理台数
- 目標
- 2030年度末
590万台/年
- 1.5℃世界に向けた今後の戦略と対応
-
- 既存プラントのM&A、新規リサイクルプラント設立により事業を拡大し、循環型社会の実現に貢献する
- 自動化・省力化を図るとともに、 操業管理システムのクラウド化による管理強化、LCA評価による環境価値可視化等にて差別化を図る
目標に対する2023年度実績
家電リサイクル年間処理台数
2023年度は新型コロナウイルス感染症平常化後の買い替え需要が期待されましたが、消費行動が「モノ消費」から「コト消費」に移ったことにより、入荷台数が減少し、3.6%減の351万台となりました。


培養タンク (K10エココンテスト「セメント排ガスを活用した藻類培養の実証試験」の関連写真)
GHG排出量実績と取り組み
2023年度のGHG削減活動
GHG排出量(単体、国内グループ会社、海外グループ会社の内訳)
2023年度の当社グループのGHG排出量(Scope1 + 2)は887千t-CO2e★でした。再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めた結果、2022年度から15千t-Co2e減少しました。
GHG排出量の内訳は、単体が42%、国内グループ会社が48%、海外グループ会社が10%でした。

- ※ 資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除く。
- ※ 2023年度までに事業譲渡等により連結対象から外れた、または外れることが決定した事業および子会社を除く。
GHG排出量(事業別の内訳)
2023年度の事業別のGHG排出量は、金属事業が66%、加工事業が9%、高機能製品事業が24%、その他事業が1%でした。

- ※ 資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除く。
- ※ 2023年度までに事業譲渡等により連結対象から外れた、または外れることが決定した事業および子会社を除く。
2023年度GHG総排出量内訳[千t-CO2e]
2023年度のGHG総排出量は、資源循環の取り組みにより生じるGHG(422千t-CO2e)および事業譲渡等により連結対象から外れることが決定している事業および子会社のGHG(363千t-CO2e)を含め、1,671t-CO2e★でした。
GHG総排出量に占めるエネルギー起源のGHGは24%、資源循環の取り組みにより生じるGHGは25%でした。
| 分類 | 単体 | 国内グループ | 海外グループ | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | エネルギー起源(燃料等) | 108 |
181 |
117 |
406 |
| 非エネルギー起源 | 47 |
66 |
21 |
134 |
|
| 資源循環の取り組みにより排出されるGHG | 170 |
252 |
0 |
422 |
|
| Scope1合計 | 324 |
499 |
138 |
★962 |
|
| Scope2 | 221 |
176 |
312 | ★709 | |
| 合計 | 545 |
675 |
450 |
★1,671 |
|
- ※ 資源循環の取り組みにより排出されるGHGを含み、2024年3月31日時点の連結子会社を含む。
- ※ 「グループ会社」は連結子会社84社(国内35社、海外49社)を含んでいます。
- ※ 排出係数として、国内電力は電力会社の調整後排出係数、海外電力は国際エネルギー機関(IEA)が公表する排出係数、燃料および蒸気は温対法の数値を用いています。
- ※ 「Scope2(間接)」は市場別(market base)排出量を表示。地域別(location base)では760[千t-CO2e]。
2023年度のScope3排出量[千t-CO2e]
| 項目 | 対象 | 単体 | グループ | 計 | 活動量の考え方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 921 | 2,402 | 3,323 | グループ外から受け入れた原材料(廃棄物原材料・副産物原材料は対象外)・取水量の物量ベースの使用量 |
| カテゴリ2 | 資本財 | 連結財務諸表と同じ | 102 | 204 | 305 | 報告対象年度における設備投資金額 |
| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 温室効果ガス排出対象組織と同じ | 54 | 108 | 162 | 燃料種別使用量、グループ外から購入した電力量および蒸気量 |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 231 | 512 | 743 | ①報告対象年度に購入した製品・サービスのサプライヤーから自社への物流に伴う排出 ・主要原材料ごとに(廃棄物原材料・副産物原材料は対象外)輸送シナリオを設定 ・国間距離はIDEA 国地域間距離データベース、その他の距離は距離検索サイトを利用し設定(一部、カンパニーへのアンケートにより回答があった距離を採用しているケースもあり) ②報告対象年度の出荷輸送のうち、自社が費用負担している製品の物流に伴う排出 ・主要出荷製品ごとに輸送シナリオを設定 ・国間距離はIDEA 国地域間距離データベース、その他の距離は距離検索サイトを利用し設定 |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 4 | 18 | 22 | 産業廃棄物量(再資源化・埋立)を対象 |
| カテゴリ6 | 出張 | 連結 | 0 | 2 | 2 | 単体については、拠点(事業所およびオフィス)別の従業員数。 連結子会社については、有価証券報告書の人員情報より、カンパニー別の従業員数 |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 連結 | 2 | 5 | 7 | 単体については、拠点(事業所およびオフィス)別の従業員数。 本社オフィスおよび本社以外のオフィスについては報告対象年度の出社割合を乗じた値を活動量とした。 連結子会社については、有価証券報告書の人員情報より、カンパニー別の従業員数 |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | 賃借しているリース資産はあるが、Scope1,2に含んでいるため、算定対象外 |
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 42 | 134 | 176 | 販売先までの出荷輸送のうち、他社が費用負担している製品の物流に伴う排出。 販売先以降最終消費者までの輸送は対象外とする 国間距離はIDEA 国地域間距離データベース、その他の距離は距離検索サイトを利用し設定(一部、カンパニーへのアンケートにより回答があった距離を採用しているケースもあり) |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 107 | 415 | 522 | 販売した製品として、カンパニー別グループ外への製品出荷量を活動量とした。 製品ごとに想定される一次加工を設定して、加工に伴う排出量を算定 |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | ー | ー | ー | ー | 販売する製品は素材や部品で、利用先は多岐に渡り、最終製品までたどるのは困難であるため、算定対象外 |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 温室効果ガス排出量以外の環境データ対象組織と同じ | 2 | 5 | 8 | 販売した製品として、カンパニー別グループ外への製品出荷量を活動量とした 製品ごとに想定される廃棄方法を設定して、廃棄に伴う排出量を算定 |
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | ー | ー | ー | ー | 賃貸ししているリース資産はほぼないため、算定対象外 |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | フランチャイズ事業は行っていないため、算定対象外 |
| カテゴリ15 | 投資 | 持分法適用関連会社 | 5,465 | 0 | 5,465 | 報告対象年度における持分法適用関連会社のScope1 + 2排出量および持分割合 |
| 合計 | ★6,931 | 3,803 | ★10,734 | |||
- ※ 原材料調達、輸送、製品出荷シナリオは2021年度実績に基づき設定しています。
- ※ 算定方法は、環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver.2.6)」を参考とし、排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)」および「国立研究開発法人産業技術総合研究所 IDEA Ver.3.4」等を参照して算定しました。
- ※ 2023年度のScope3排出量は、2024年3月31日現在における、当社および連結子会社46社のデータを反映しています。
各事業における主要な取り組み
当社の製造事業所・⼯場は、徹底した省エネルギーの追求を重要課題と捉え、省エネ活動を進めています。
具体的には、燃料の⾒直し、未利⽤エネルギーの利活⽤、⼯程・設備の改善、⾼効率機器の導⼊、機器仕様の適正化、設備運転制御・操業形態の⾒直し等の視点で活動を⾏っています。本社・⽀店・営業所や、研究所等の⼩規模な事業所でも、LED照明導⼊等の省エネの取り組みを継続しています。
気候変動に関するサプライヤーエンゲージメント
当社グループでは、GHG排出量のうちScope3(カテゴリ1,3,15)の削減目標として、2030年度に2020年度比で22%削減を掲げています。また、CFPの算定も順次進めており、今後はその削減にも取り組んでいきます。これらの実現のためには、当社事業による排出量のみならず、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減を推進することが重要です。当社は、サプライチェーン全体でのGHG排出量削減に向け、サプライヤーとの関係構築を進めています。具体的には、Scope3排出量の約3割を占めるカテゴリ1に関連する銅精鉱サプライヤーに対してエンゲージメントレターを送付し、両社の地球環境課題への取り組み状況やGHG排出量削減目標と削減計画に関する情報の共有、面談等での意見交換を行っています。これらの取り組みは今後も継続し、対象サプライヤーを拡大する予定です。
また、銅精鉱サプライヤーのうち、英国ロンドンに本社を置く英国上場の多国籍鉱山会社であるAnglo American plcとは、銅関連製品のサプライチェーン全体において、透明性を確保し、持続可能で責任のある製品を提供するための取り組みを進めるための覚書を締結しました。カーボンニュートラルの実現に向け、自動車のEV化や再生エネルギー由来電力の利用拡大が推進されており、それに伴って銅の需要が増大すると予測されています。世界的な銅需要の高まりとともに、それらの供給がよりクリーンで持続可能であることが望まれています。このような市場の要望に応えるための取り組みを、ともに進めていきます。
物流資材部門を通じた調達におけるサプライヤーとの取り組みについては、「サプライチェーンにおける人権への配慮」をご参照ください。
- Scope3削減に向けた取り組み
MUCCのカーボンニュートラルへの取り組み -
当社グループのScope3のカテゴリ15排出量として、持分法適用関連会社であるUBE三菱セメント(株)(以下、「MUCC」)の Scope1,2排出量の50%(持分割合分)を計上しています。この排出量はScope3の約60%(2020年度実績)を占めており、MUCCの排出量削減は当社グループのScope3削減に大きく寄与します。MUCCは、2023年4月に発表した中期経営戦略「Infinity with Will 2025~MUCCサスティナブルプラン 1st STEP~」の中で、「地球温暖化対策の推進」を最重要課題のひとつと位置付けています。2023年度は組織体制の整備による推進体制強化のため、カーボンニュートラル技術推進室および推進委員会を設置しました。
2050年のカーボンニュートラルおよび中間目標である2030年時点でのCO2排出量40%削減(対2013年比)達成に向け、多様な取り組みを進めています。
「CO2を減らす」では、清水建設(株)とセメントの約80%を高炉スラグ微粉末に置換した環境配慮型コンクリートを共同開発しました。また、世界初のセメント製造プロセスでのアンモニア混焼実機試験に着手しました。
「CO2を使う」では、北九州循環経済ビジョン推進協議会の廃コンクリートの炭酸塩化利活用分科会に参画し、セメント工場のCO2と廃コンクリートを用いたCO2固定化リサイクル品を建設工事に適用していくためのビジネスモデル確立を目指しています。
「CO2を溜める」では、セメント製造プロセスのカーボンニュートラルに向けたマレーシア・日本間でのCCSについて、三井物産(株)との共同検討を開始しました。また、大阪ガス(株)とのCCUSに関する共同検討についても着手しています。
当社はScope3削減に向け、今後もMUCCとのコミュニケーションを深めていきます。
- 金属事業部門の事業所において
再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを大幅に加速
~8割の事業所で2024年度に完全導入~ -
当社グループは、当社の資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除いたGHG排出量(Scope1およびScope2)を対象に、2030年度までに2020年度比で47%削減することを目標としています。その達成に向けて、省エネルギーの推進や、CO2排出量削減に寄与する燃料への転換などとあわせ、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めています。
当社グループのGHG総排出量(資源循環の取り組みにより排出されるGHGを含む)のうち、電力起源の排出量は、全体の38%(2020年度実績)を占めています。当社グループの国内電力消費量の約60%を占める金属事業部門では、購入電力のうち、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えをさらに加速させ、8割の事業所においてその計画完了時期を2024年度に最大11年前倒しし、また、直島製錬所および小名浜製錬所においても2028 年度に7年前倒しすることにしました。
物流における取り組み
2023年度の輸送におけるCO2排出量は、単体は18,610t(2022年度比500t増)となり、グループ会社分は集計対象の変更があり、5,074t(2022年度比7,490t減)となりました。単体+グループ会社のCO2排出量合計は23,684t(2022年度比6,990t減)となりました。一方、エネルギー消費原単位※は、単体は23.05kℓ/百万トンキロ(2022年度比 約2.6%悪化)となりましたが、単体+グループ会社の合算値では23.03kℓ/百万トンキロ(2022年度比 約12.5%悪化)となりました。 今後も、モーダルシフト推進や積載率改善等による輸送省エネに努めるとともに、グループ全体での物流最適化を通じて、非化石エネルギー活用などの環境負荷を抑制する物流の構築を目指します。
輸送モード別CO2排出量(単位:t-CO2)
| 2022年度 | 2023年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | グループ 会社 |
合計 | 単体 |
グループ 会社 |
合計 | |||
| 物流CO₂排出量 | 総量 | 18,109 | 12,564 | 30,673 | 18,610 | 5,074 | 23,684 | |
| 内訳 | トラック | 11,103 | 4,936 | 16,039 | 11,759 | 3,416 | 15,175 | |
| 船舶 | 6,960 | 7,625 | 14,585 | 6,800 | 1,655 | 8,455 | ||
| 鉄道 | 12 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | ||
| 航空 | 35 | 0 | 35 | 47 | 0 | 47 | ||
- ※ 使用エネルギー量を原油量換算(kℓ)し、輸送トンキロ(百万トンキロ)で割った値
脱炭素社会実現に向けた取り組み
「脱炭素社会実現に貢献する製品やサービス」
当社グループは、気候変動への対応を脱炭素社会の実現に向けた重要な経営課題のひとつとして捉え、環境負荷低減を考慮したものづくりや地熱等再生可能エネルギーの開発・利用促進に取り組んでいます。
- リチウムイオン電池リサイクル技術の確立に向けたパイロットプラントの建設
~ブラックマスからのレアメタル精製事業化への次のステップへ~ -
リチウムイオン電池(LIB)の材料であるリチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルは近い将来の供給不足が懸念され、産業界全体における成長戦略の重要な課題となっており、地下資源の開発に加え、材料のリサイクルや代替材料の開発などの対策が行われています。
当社においては、ブラックマス※8からリチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルを回収・精製する事業化に向けて、これまで小規模試験による技術開発を行ってきました。このたび、一定の成果が得られたことから、次のステップとして、福島県いわき市の小名浜製錬(株)小名浜製錬所の敷地内にパイロットプラントを建設して、ブラックマスからのレアメタルの高効率回収の事業化に向けた、さらなる技術開発に取り組みます。
なお、本パイロットプラントの建設に伴う技術開発については、経済産業省から「重要鉱物の供給確保計画」の認定(供給確保計画認定番号:2023重要鉱物第1号-1)による助成を受け進めていきます。パイロットプラント概要
原料:LIB由来のブラックマス
生産物:電池グレードの炭酸リチウム、硫酸ニッケル、硫酸コバルト
稼働開始時期:2025年
場所:小名浜製錬(株)小名浜製錬所敷地内- ※8 LIBを放電・乾燥・破砕・選別したリチウム、コバルト、ニッケルの濃縮滓。
- xEV用全固体電池向け材料の新たな製造技術開発に成功
-
硫化物系固体電解質は、全固体電池向けの固体電解質の中でもイオン伝導率が高く、その入出力性能の高さから自動車の航続距離の延長や充電時間の短縮が期待されており、xEV用全固体電池の有力材料とされています。しかしながら、量産性の低さと取り扱いの難しさから全固体電池への実用化に向け大きな障壁となってきました。
当社は、これまでのさまざまな非鉄金属材料に関する技術開発やノウハウを活かし、硫化物系固体電解質の新たな製造技術として、硫黄を含む原料を混合し、加熱炉で焼成するだけで目的物質を合成できるシンプルなプロセスの開発に成功しました。この新たなプロセスによって製造規模を大きくしやすくし、硫化物系固体電解質の事業化に向けた検討を進めます。現在、本プロセスで合成した硫化物系固体電解質を、特定のお客さまに対してサンプル提供し、事業化に向けた評価を進めています。
- 3Dプリンタ技術を用いた2層構造を有する新たなチタン製電極を開発
~高電流密度対応で効率的な水素製造に利用可能な新素材~ -
当社と横浜国立大学 光島重徳(工学研究院教授、先端科学高等研究院先進化学エネルギー研究センター長)らのグループは、共同研究開発において、高電流密度条件下においても高効率で作動可能なチタン製の水電解電極を新たに開発しました。 水素は脱炭素社会の実現に向けて、CO2を発生させないクリーンエネルギーとして需要が高まっています。水素製造技術の1つとして、低環境負荷で高効率な水素製造技術である「固体高分子型(PEM)水電解」が注目されています。この電解技術は、100℃以下の純水および電気の力で高純度な水素を製造することができます。しかしながら、システムコストは高く、コスト負荷の大きな酸化イリジウムといった貴金属触媒の使用量低減が求められています。
そのような背景の中、NEDO*9の水素利用等先導研究開発事業を受託し最先端の電極評価技術を有する横浜国立大学と、難易度の高いチタン材料の焼結技術を有する当社は、新規のチタン製水電解電極の開発に取り組みました。
NEDO事業の成果である電解槽の性能を電解質膜の抵抗分極、電極触媒の活性化分極、電極の集電抵抗や拡散過電圧などの要因別に分離して解析する評価技術を利用し、水電解電極の高効率化には、異なる機能を有する微細な2層構造とすることが有効であることを見い出しました。しかしながら、構造が異なる2層から成る電極は、各電極の層に必要な空間設計のスケールが異なるため、従来の製法では一体化して製造することができませんでした。そこで当社は解像度並びに空間設計自由度が高いバインダージェット方式*10の3Dプリンタを採用し、2層の精緻な電極製造に必要な新たなチタン焼結技術の研究開発を行い、2層構造を持つ電極の製造を可能としました。
この新開発の水電解電極を利用することで、高電流密度条件下においても、高効率に水電解システムを作動させることができます。さらに、貴金属触媒などの使用量削減による水素製造コストの低減にも寄与します。
今後は実用化に向けて、最適な電極構造の開発・試作を続けていきます。- ※9 新エネルギー・産業技術総合開発機構。
- ※10 薄く敷いた粉末に結合剤を塗布しながら積層し、乾燥炉で成形体として固め、焼結して部品を製造する方式。